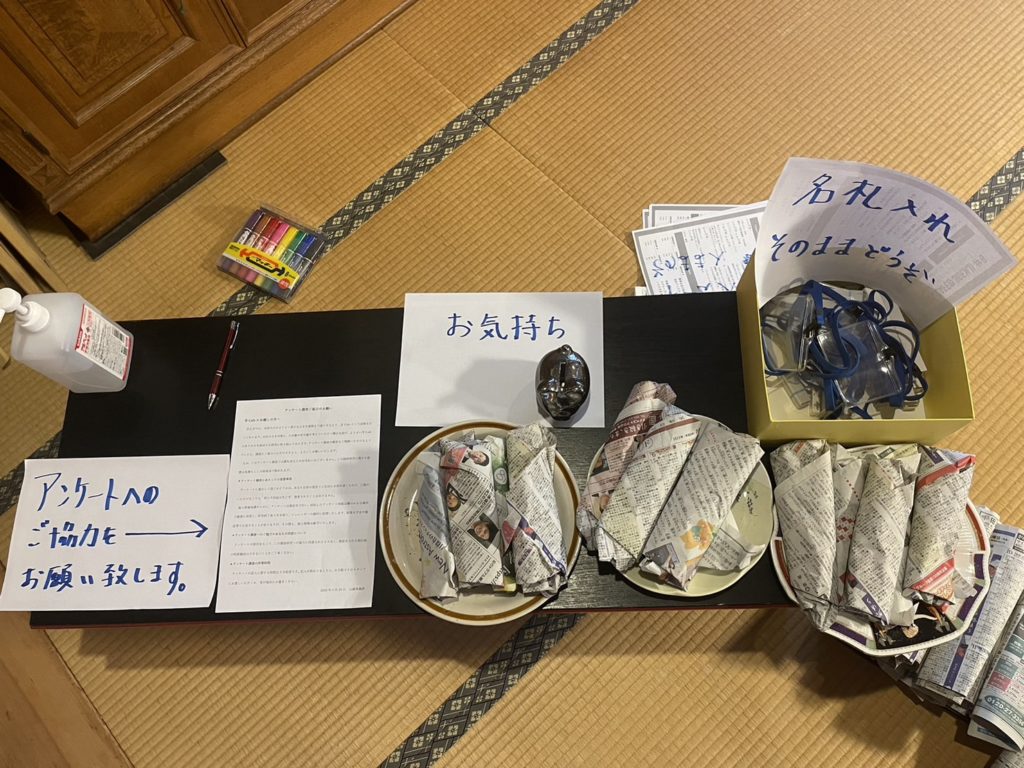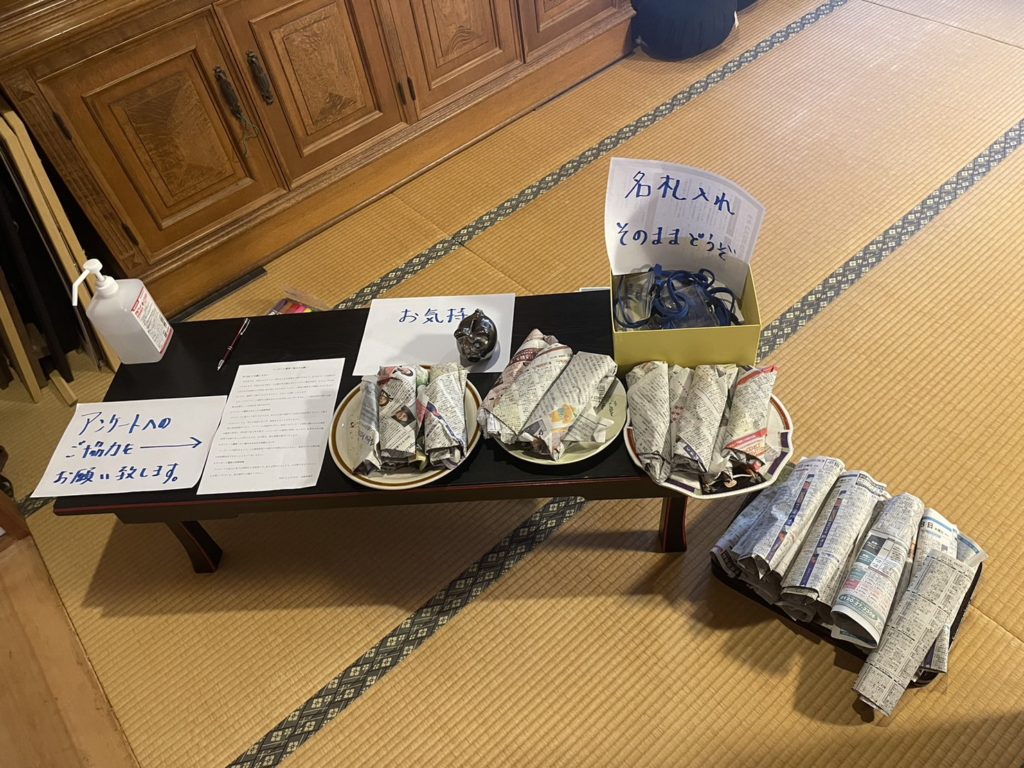コロナ禍で中断をした寺Caféも、おかげさまで10回目を迎えることが出来ました。ご参加頂いた皆さま、自分のこととして真摯に、ともに運営して下さるスタッフ皆さまにあらためて、御礼申し上げます。ありがとうございます。
今回は「戒名」についてです。戒名は死後にいただくもの、と思われがちですが、生きているうちに授かることが本来です。今までの人生を振り返りながら、これからどのように歩んでいくのか、その指針となるものが戒名です。
自元寺は『誰でも頼れる安心のお寺を探す』まいてらに参加させていただいており、コロナウイルスによる時期にはオンラインにて、まいてらカフェを行いました。
様々なテーマを設けて開催しましたが、何より私たち僧侶が多くを気づかされ、学ばせていただく時間であり、参加頂いた方からも、有意義だったというお声が大多数でありました。
コロナウイルスに関することが、完全に終息しているわけではありませんが、あのじかんを経たわたしたちだからこそ、「どう生きるのか」を想う気持ちは深まっていると思います。
まいてらを主宰される井出悦郎さん、多宗派、県内外から集まったお坊さんと対話しながら、ご自身の戒名を考えることで、人生を充実させるヒントが見つかるかもしれません。是非、この機会に戒名をいっしょに考えてみませんか?
日時:令和5年10月22日(日) 14時~16時
場所:白砂山 自元寺(北杜市白州町白須1364)
申込:下記QRコード、電話(0551-35-2245)、メールにて(HPの下よりメッセージをお送りいただけますのでご活用ください)
定員:40名、参加費無料